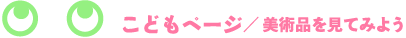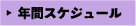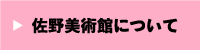 |
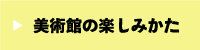 |
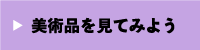 |
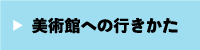 |
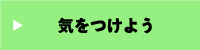 |
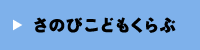 |


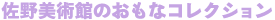
佐野美術館のコレクションは、日本や中国(ちゅうごく)、朝鮮(ちょうせん)の美術品を中心に、陶磁器(とうじき)や彫刻(ちょうこく)、日本画(にほんが)、能面(のうめん)など約2,500点です。とくに日本刀は多くの名品があります。おもなコレクションのみどころを紹介します。


中国・唐時代 8世紀
今から1300年位前の中国で作られたやきものです。瓶は、食べ物や水などをいれておく器(うつわ)です。
 |
 |
 |
| 竜の形の把手 竜が向かい合って、瓶の口をく わえています。竜は、中国で生まれた想像上の生きものです。すべての生き物の王さまで、世の中によいことが起こるときに現れると考えられました。絵に描かれたり、やきものの模様(もよう)などにも好んで使われました。 |
三彩の名はここから 緑、白、褐色(かっしょく)の三色のうわぐすりがかかっています。とけて流れたり、まじり合ったりしてきれいです。 |
文様は半分だけ 王さまや貴族など、身分(みぶん)の高い人のお墓に、いっしょに埋(う)められていました。実際に使われたものではないので、文様は上半分までしか描かれていません。 |

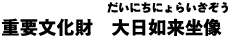
平安時代 12世紀
今から900年くらい前の日本で作られた仏像(ぶつぞう)です。大日如来は、どんな闇夜(やみよ)も明るく照らす仏さまで、その姿は宇宙そのものである、といわれます。

 |
 |
 |
| しずかなお顔 仏像は仏教の生まれたインドから中国へ伝わり、日本へやってきました。目を細く開けて遠くを見つめ、口もとはわずかにほほえんでいます。この世を大きな愛でつつむ、しずかなお顔です。 |
手の形は何? 仏さまによって手の形がちがいます。大日如来が結ぶ手の形は、智拳印(ちけんいん)といいます。あらゆる修行(しゅぎょう)を終えて、まことの仏となった印(しるし)です。 |
仏像は花の上にすわっています。大日如来が坐(すわ)っている台は蓮華(れんげ)の形をしています。蓮華は泥水(どろみず)の中から美しい花を咲かせます。その清(きよ)らかさは仏の姿そのものです。 |
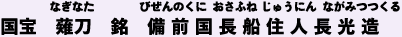

鎌倉時代 13世紀
今から700年くらい前につくられた日本刀です。作者は長光という刀づくりの名人で備前国(びぜんのくに)(今の岡山県)の人です。
今から700年くらい前につくられた日本刀です。作者は長光という刀づくりの名人で備前国(びぜんのくに)(今の岡山県)の人です。
 |
長い刃 刃の長さは1メートルくらいあります。刃先(はさき)がすっと反り返っていてかっこいいです。 |
 |
不思議なマーク 長光が、持つところに自分の名前と梵字(ぼんじ)を刻んでいます。日本刀に刻んだ名前を銘(めい)といいます。梵字は古いインドの言葉で、一文字で仏そのものを表します。刀には仏のような特別な力が宿(やど)っている、と考えられていました。 |
 |
どうやって使ったの 柄(え)や刃が長いので、相手から離れたところで戦うことができます。薙刀は戦いでたくさん使われたので、きれいな姿で残っているものはほとんどありません。 |
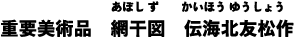

桃山時代 17世紀
今から500年くらい前の日本で描かれた絵です。作者は海北友松という画家と伝えられています。近江国(おうみのくに)(今の滋賀県)の人です。
今から500年くらい前の日本で描かれた絵です。作者は海北友松という画家と伝えられています。近江国(おうみのくに)(今の滋賀県)の人です。
 |
 |
|
| キラキラの絵 魚をとる網(あみ)を干した砂浜と、船が浮かぶ海が描かれています。砂浜や雲のところは金箔(きんぱく)で表しています。 |
折りたためます 屏風(びょうぶ)に描かれています。屏風は折りたたんで持ち運ぶことができます。部屋の仕切(しき)りに使ったり、しまっておくのにも便利(べんり)です。 |
|
 |
季節の変化 芦(あし)の葉を右から左に見ていくと、緑の葉から穂(ほ)がついて葉が枯(か)れ、雪がふっています。 |

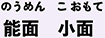
江戸時代 17世紀
今から400年くらい前の日本で作られた能面です。能面は歌と舞(ま)い、楽器の演奏(えんそう)をともなった劇(げき)「能」に使われるお面です。

| なぞのほほえみ 上から見ると笑っていて、下から見ると悲しんでいるように見えます。面(おもて)をつけた役者は面の角度を少しづつ変えて、表情(ひょうじょう)を変化させました。 |
ウラに秘密が ウラには面をつくった人のしるしが彫(ほ)ってあります。右上の放射状(ほうしゃじょう)の彫りあとです。 |
どんな劇かな 歌人の藤原定家(ふじわらのていか)と天皇(てんのう)家のお姫さま、式子内親王(しょくしないしんのう)との恋物語『定家(ていか)』に使われたと考えられています。 |
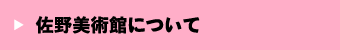 |
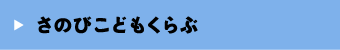 |