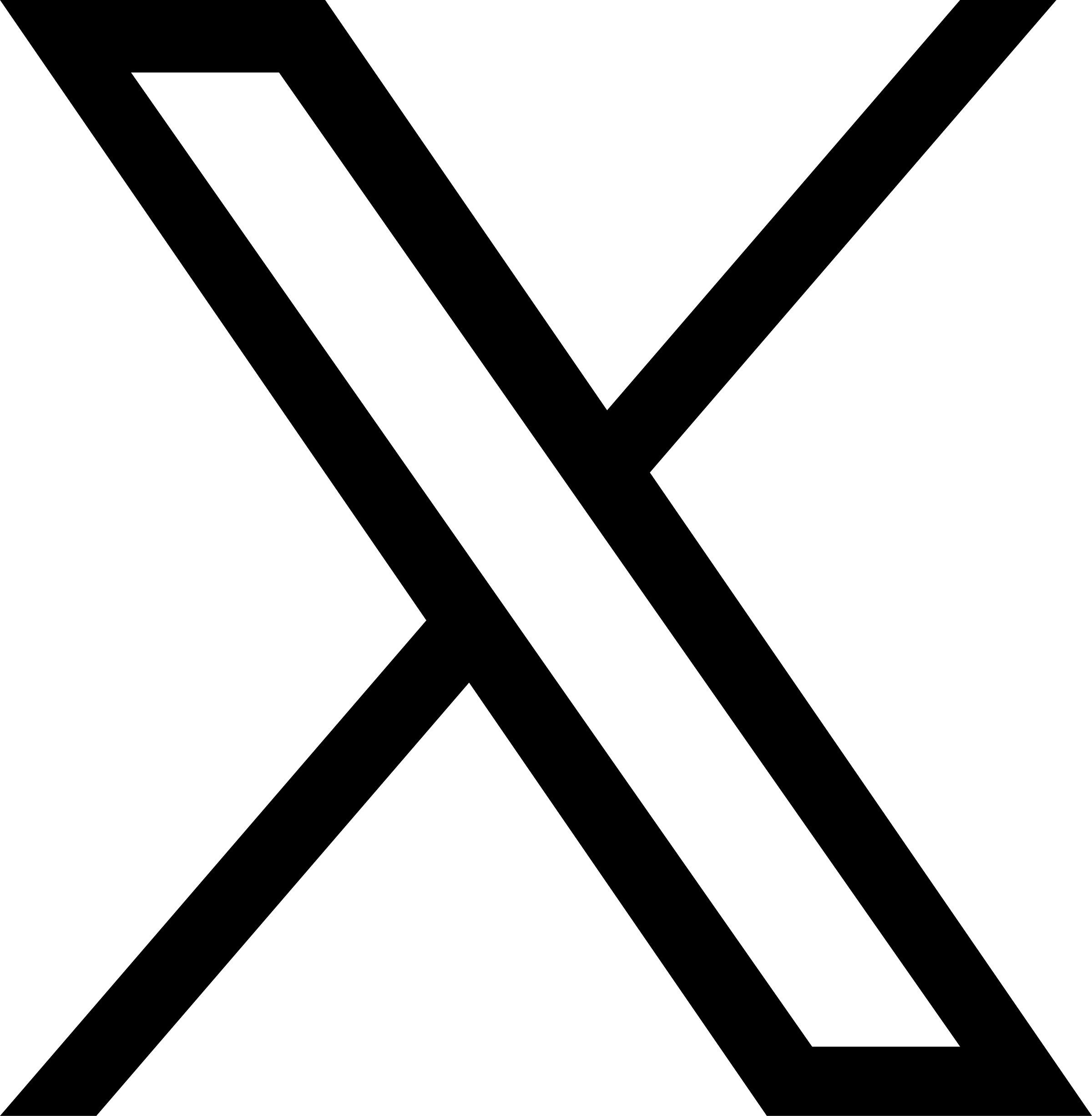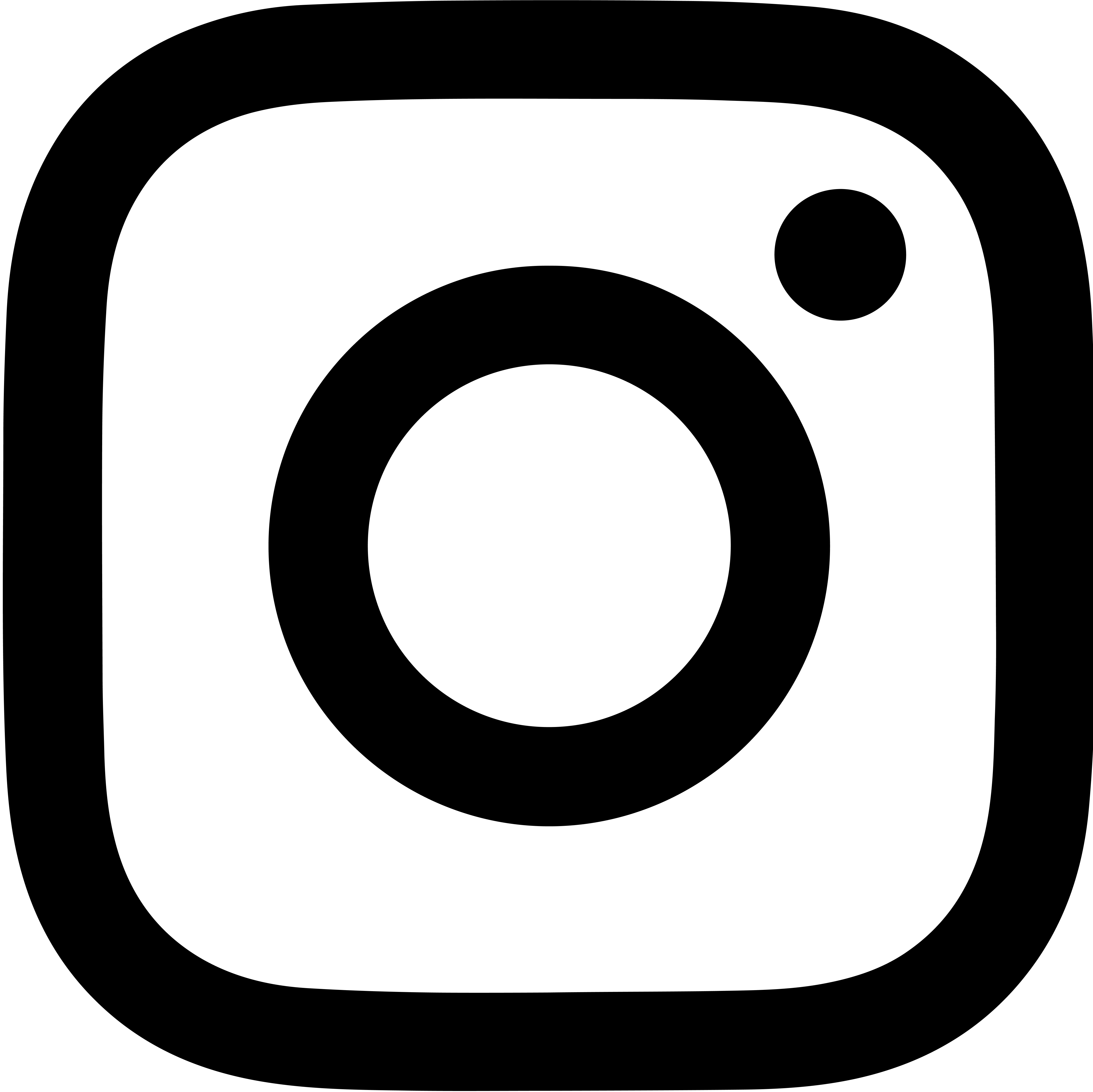櫂図小柄 銘 祐乗作 光昌(花押)
(かいずこづか めい ゆうじょうさく みつまさ(かおう))
後藤家十四代揃金具(倶利伽羅龍三所物)
(ごとうけじゅうよんだいそろいかなぐ(くりからりゅうみところもの))
月影透鐔 無銘 甲冑師
(つきかげすかしつば むめい かっちゅうし)
塔橋花図鐔 無銘 鎌倉
(とうはしはなずつば むめい かまくら)
茗荷蔦透鐔 無銘 尾張
(みょうがつたすかしつば むめい おわり)
茶席図鐔 銘 西陣住人埋忠重長
(ちゃせきずつば めい にしじんじゅうにんうめただしげなが)
松樹透鐔 無銘 林
(まつじゅすかしつば むめい はやし)
鶴丸透鐔 無銘
(つるまるすかしつば むめい)
道成寺図縁頭 銘 大森英房(花押)
(どうじょうじずふちがしら めい おおもりてるひで(かおう))
鶏図縁頭 銘 石黒政明(花押)
(とりずふちがしら めい いしぐろまさあき(かおう))
鷹捉雉子図縁頭 銘 津尋甫
(ようそくきじずふちがしら めい つじんぽ)
枝梅図鐔 銘 長常(花押)
(えだうめずつば めい ながつね(かおう))
枝梅水仙図縁頭 銘 一宮長常(花押)
(えだうめすいせんずふちがしら めい いちのみやながつね(かおう))
幽霊図小柄 銘 夏雄刻
(ゆうれいずこづか めい なつおこく)
秋草虫尽図揃大小金具
(あきくさむしづくしずそろいだいしょうかなぐ)
作者
後藤一乗(ごとういちじょう)
生没年
1791〜1876
国
日本
時代
江戸時代(19世紀)
形質
笄・小柄・縁/赤銅魚々子地高彫
目貫/赤銅容彫
員数
1揃
法量
笄/長 21.3 cm
小柄/長 9.5 cm
縁/幅 2.1 cm 長 3.9 cm
目貫(蜻蛉)/幅 1.5 cm 長 4.3 cm
解説
小柄、笄、大小の縁、目貫2組が一揃いとなり、秋草と秋の虫の揃いの意匠である。小柄、笄、縁には、一乗作の特徴でもある整然と並ぶ粒の細かい赤銅魚々子地に菊や薄、女郎花などの秋草に蜻蛉や蝶が遊ぶ様子が優美に高彫色絵され、2組の目貫は蝶、蜻蛉、鈴虫、蟋蟀、飛蝗が写実的に可憐に容彫される。後藤一乗は、室町時代より将軍家の御用を勤めた金工の名門である後藤家最後の名工。絵画にも秀で、後藤家伝統の格式の高さと、独自の瀟洒で雅味のある絵画的な作風で、加納夏雄とともに幕末明治期の金工を代表する作家である。