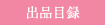人の世は争いと和解の連続である。そしてその過程において武力が用いられてきたこともまた、疑いのない史実である。今回の展覧会のテーマである兜や刀装は、そもそもはこれらの武力から身を守り、また攻撃性を増すといった実用目的で発生し、その祖型は遠く古代に遡る。その様式変遷については到底ひとことで語れるものではないが、時代の要請に応じさまざまに変化を遂げてきた。
「変わり兜」を知るためにはまず、「変わっていない兜」を確認しておかなければならない。本展において、その両者はあくまで相対的・主観的な比較であるが、また、大多数が共通して感じる印象でもある。まずは、「兜」と聞いて多くの人が想起するであろう、平安時代以降の代表的様式である星兜と筋兜からひもといてみよう。
刀剣外装は後代の改変を受けやすく、鎌倉~室町期について、時代の姿を捉えることは難しい。絵巻に描かれる蛭巻(ひるまき)の薙刀を今に伝える誉田八幡宮の薙刀拵や、柄に刳り込まれた半月形が呑口式の面影を漂わせる腰刀拵など、中世の刀装様式を今に伝える作例は当時の様式を伝えるものとして大変稀少なのである。
戦国アバンギャルドとその昇華
兜 KABUTO
織田信長、次いで豊臣秀吉が天下統一を目指していた群雄割拠(ぐんゆうかっきょ)の時代。下克上も夢ではない実力主義の世界に生きた猛者(もさ)たちは、あまたの逸話とともに新たな時代の扉を開きました。そして彼らの型に捉われない生き様は、戦の晴れ姿である兜に、かつてない斬新な形を生み出しました。
伊達正宗は額に三日月を頂き、黒田長政は雄々しい水牛の角を生やした兜をかぶる。その発想力・具現力が生み出した鮮烈な造形は、単なる奇抜さだけでなく、高い見識によって洗練された緊張感を漂わせています。
続く江戸時代、その独創性はより細密さを増し、刀を納める鞘(さや)やその周辺の小柄(こづか)、小刀、鐔(つば)などで新たな発展を見せました。
戦国の世に花開き、太平の世で成熟した、サムライ・アバンギャルドをご堪能ください。
会期中一部展示替えがあります。
プロローグ 変わり兜前夜
第一章 威厳と異形
戦国時代、戦に臨む武将たちは頭上に載せる兜の造形に、神仏の加護を求め、或いはおのおのの威厳の象徴を追求した。時にライバルよりも大きく、長く、より格好よく、と競い合うように進化を遂げたのであろう。大将が陣床几に座りシンボルとして存在するという戦闘の場において、これらの独創的な兜はいわば自軍のトレード・マークとして機能したに違いない。
鐔の世界では、鉄鐔を中心にさまざまな時代の装飾が付加されるようになった。室町期には水墨画風の文様を浅い彫りで表出した鎌倉鐔、鍛鉄を生業とする甲冑師や轡(くつわ)師たちが身近な文様を透かして作った鐔、鉄地に真鍮で多彩な文様を象嵌した平安城象嵌等が登場する。特に戦国時代から桃山時代にかけては、為政者の拠点であった京は鐔づくりの一大拠点であったのであろう。それ以前の鐔の美が無作為の美であったとするならば、埋忠明寿(うめただみょうじゅ)は鐔に対し、意識的に芸術性を追求した最初の鐔工であった。またこの時期には信家や金家、平田道仁といった個銘を伴う鐔工たちが登場し、新時代が幕を開ける。
第二章 桃山から江戸へ
桃山時代に開花した兜と刀装の造形力は、江戸時代にかけてゆるやかに着地していく。本章では、桃山時代の残像を残しつつあった時代から、変わりゆく時代の混沌を越えた泰平期にかけての様相を概観したい。
大名家では初代の兜を祖型とし代々これを継承することに価値が見いだされる。これは初代に対する敬意の現れであり、また藩の結束の強化に資するものであった。
また泰平期の刀装具については、刀装金工が大名家という安定的に注文をもたらしてくれる庇護者を得たことが大きい。そのひとつのあらわれとして、お抱え金工、或いは、御用を受けていた金工がある。作品と旧蔵者が対応できる作品はごく一部であり、かつ、受注関係まで追える物は皆無に近いが、江戸時代の刀装具が高い水準を保ちながらさらに技術面・表現面双方で発展を遂げた背景には、世情の安定と安定的な用命という側面は見逃せない要素なのである。
第三章 鉄の造形
多様な技法で多様な意匠を表した変わり兜は魅力的であるが、これらの多様性を頭の中に整理して理解することは難しい。また、刀装具といっても鉄鐔と彫金ものでは制作集団も異なれば、愛好家集団も異なる。ならば本章では「鉄」という切り口でその一部を切り分け、兜と鐔に共通する「鉄」の魅力にアプローチしよう。
江戸時代になって飛躍的に制作レベルが向上した彫金ものとは異なり、鉄鐔の世界は基本的な技法が変わるわけでもなければ、細密さや色鮮やかさで彫金ものの刀装具に勝てるわけでもない。しかし鉄は、刀身のように表面を鏡面的に磨き上げることもできれば、故意に錆を付けてマットな仕上がりにすることもできる。また、異なる地鉄を組合わせることで板目のような地肌を創出することもできる。ひとつの金属でありながら、加工方法によってこれほど異なる表情を見せることが出来る素材は他にないだろう。そこが鉄の妙味なのである。水墨画にも似た鉄の枯淡な味わいは、彫金鐔の細密さとは対極的なところにある美学なのである。
第四章 技術の爛熟とリアリズムの追求
現在残されている奇抜な兜の多くは、江戸時代に作られたものである。それは、戦国時代の異形の兜を父とし、江戸時代に高まった工芸技術を母として成立したと考えるべきもので、いうならば争乱と泰平の双方によって、奇跡的にもたらされた産物であった。その点において、江戸時代の工芸技術の向上という要素は、変わり兜を捉える上で不可欠な視点である。そこで本章では、変わり兜の隆盛を支えた工芸技術の進展という視点、また、当時の潮流であったリアリズムへの追求がもたらした「質感の擬似再現」というキーワードから見つめてみよう。
高度な工芸技術と粋な趣向による「質感の擬似再現」は本章で扱う兜・刀装の多くに共通する趣向であり、時代の様相でもあった。この時期刀装の世界においても変わり塗りや変わり鐺(こじり)、変わり栗形といった、変わり兜に呼応するような作品も散見される。これらはもはや実用などという無粋な目的ではなく、高度な工芸技術と粋な趣向に満ちた「質感の擬似再現」を愉しむために作らせたとしか考えられないものであった。ひるがえって江戸時代の変わり兜を見たとき、何に駆り立てられてこのような兜が生まれたのかということへのひとつの答えが見えてくると思うのである。